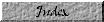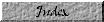|
祭りが始まる
真夏の夜の夢のような
祭りが始まる
時を止めた常春の地に響く、賑やかな歓声とさざめくような笑い声。
忘れ去られて久しかったこの夏の日を、誰ともなく祝おうと、見慣れた貌が一所に集まった。
「この地で初めて逢ってから、すでに10余年を越えたか……そなたの深慮、これからも頼みにしているぞ」
「昔も今も、変わらぬな……できうればそのままの御前で居てくれ」
「いつまでも心安らかに日々を送れますよう祈っております」
「読書なさるのも良いですけれど、今度皆で外へ遊びに行きましょうね!」
「夜の静寂、ふたりきりの逢瀬を願いたいものだな。…勿論、言葉の棘は抜きにして」
「どっかの莫迦狼に襲われそうになったら、いつでも私が護ってあげるから、安心してねっ☆」
「もーちっと運動神経つけろよな。そしたら、エアバイクのリアシート乗せてやるぜ」
「新しい花がもう少しで咲きそうなんです! 鉢植えにして贈りますねv」
誕生日を覚えていてくれたことに驚き言葉を無くす彼を取り巻き、口々に祝いの言葉やらなにやらを贈る。
まったく閉ざされた空間で、しかも下界の歴史に触れることなく過ごせるのならば、自分がまだ地に住まう民であった頃のこともあまり思い出さなくて済むのかもしれない。女王陛下の治める宇宙に存在する様々な惑星を、時として観測調査しサクリアの配分調整をしなければならないという立場は、過去の自分が居た『時間』というものを忘れさせてはくれなかった。
調査のため資料を紐解けば、よく見知っていた筈の年号が遥か過去のものとして扱われていることもしばしば。連鎖反応的に今までに下界で流れた月日を思えば、郷愁と共にやりきれなさが心に覆い被さってくる。
それなのに、自分が聖地において体感した月日というのは、遥かに遥かに短いもので。
どちらかが虚構でどちらかが現実であるかのような錯覚すら覚えてしまう。本当はどちらも現実であるのに、両者間の均衡が取れずに瓦解する時間間隔。常春という聖地の気候も手伝って、ともすれば月日の流れというもの自体を忘れてしまいそうになる。
流れを感じるとすれば、唯一、曜日の呼称だけ。
そんな日々を繰り返すうち、いつしか月の感覚も無くなり、自分の誕生日すら意味を成さなくなっていく。
―――――――それなのに。
「僕、ケーキを焼いてきたんです」
「それでは私は紅茶を淹れて参りましょう。……ルヴァ様、済みませんが火を使わせて戴きますね」
「テーブルクロスは私が持ってきたよ〜ん♪」
ふぁさっと細かいレースのテーブルクロスが広がると、それだけで部屋の中が明るくなった。
「私は料理を持って来させたのだが……ああ、そちらの机に並べておいてくれ」
「秘蔵のワインを持ってきたんだが、飲むだろう? ルヴァ」
古びたラベルからそれと判るワインを机の上に並べる。紅い髪の背後からそうっと伸びてきた手を、ぱしっと叩く。
「ってーなっ、なにすんだよおっさんっ」
「……お子様はジュースでも飲んでいることだな」
「んだと、てめぇっ!」
「こんなところで喧嘩始めたりしないでくださいよ。俺達はこっちのを飲みますから」
そう言いながら並べられたのは、ノンアルコールのシャンパンだった。おもいっきり詰まらなさそうな貌をして憚らない銀糸に、栗色の髪が耳打ちする。
「ワインには負けるけど、これ、実はアルコール入ってるからさ」
「おめー……偶には気ぃ利くじゃねーか」
「なになに? ふたりでなに話してるの?」
貌を見合わせてにいっと笑うふたりに気がついて、金の髪が間に割って入る。
ぎゃいぎゃいと騒ぐ3人を横目に、黒衣がゆらりと揺れた。
「食後にと思い、果物を持参した……」
果物の載った籠を机に置く長身を見上げながら、年少の3人組が一歩引く。
「あ……そーだ。ルヴァにやろうと思って持って来たんだけどよ……これも使うか?」
傍に控えていた執事ロボットが、大きな箱を抱えて持ってくる。がさがさと包みを開けると、なかから蓄音機が現れた。
「あら〜、なっかなかアンティークで御洒落じゃない? 趣味良いわね、少年ッ♪」
「わ…っ…って、めぇっ! ひとの頭撫でんじゃねぇっっ!!」
目を輝かせて蓄音機を眺めるルヴァの隣で、また小競り合いが始められる。
賑やかな賑やかな、ルヴァの誕生を祝う席。
気が狂うかと思われるほどの長い時間を過ごしながら、彼の誕生日を指折り数えて待ち続け、まるで事前に示し合わせたのではないかと思ってしまうくらいのタイミングで私邸に集まってきた8人の守護聖達。祝い方はそれぞれだけれど、根本的な気持ちは皆一緒だった。
蓄音機から流れてきた曲は、以前ちょっとした話のなかで彼に好きだと言ったことのある静かな曲。そんな些細なことまで覚えていてくれる。真綿で首を締められるかの如きこの聖地での暮らしの中、誰かの為に心を砕く、その温かさに青鈍の瞳が潤んでいった。
皆一緒に居られること
必然に似た偶然で守護聖に選ばれこの聖地で出会ったこと
―――――――この世に生を受けたこと
今日のこの日は
この日だけは
感謝と祈りを捧げてもいいと
誰もがそう思っていた
祝いの声
祈りにも似た、祝いの声
永の倖を願う声
夏の夜の夢を楽しむかのように賑やかな声はいつまでも途切れることはなく、夜遅くまで温かな灯りが窓辺から闇を照らしていた。
<FIN>
|