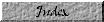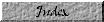|
庭園の花壇。時折緑の守護聖が花達の世話をしにくると噂のある場所。『花相手の詩は陳腐』なのか、滅多に庭園へは脚を運ばない感性の教官の姿が、常春の温かい風に誘われたのだろう、珍しく見かけられた。
「こっちにも、蕾がありますよ!」
「どれどれ………あぁ、本当に。ちゃんと蕾をつけることができて、よかったですねぇ」
横顔を覆う白い布。一陣の風がそれを揺らして、穏やかな微笑を露わにする。目にした瞬間、群青の髪が揺れた。
視線の先にあったものは、柔らかな青鈍の眼差し。
きっかけは時として、酷く単純かつ簡単な形であらわれる。
だから『こそ』、きっかけはきっかけと成り得る。
『執着』に『虚飾』は、必要ない。
◇ ◇ ◇
かさりと足元で、落ちて枯れかけた葉が音を立てる。ほんの少しそれを気にしながら歩を進めていくと、暗く沈みかけた木立の向こう側に白い人影が揺れた。細い眉を上げながら、小さく溜息。息を吸って、もう一歩。
「ルヴァ様、こんなところでなにをしてらっしゃるんですか?」
声をかけられて、傍目にも判るくらいにびくぅっと肩を跳ね上げる。その反応が想像以上に想像通りで、声をかけた張本人がくすりと微笑った。
「あー……セイランじゃないですか〜。貴方こそ、どうしたんですか?こんな処に…」
はぐらかそうとするやんわりとした笑みを一瞥して、すいっと視線を巡らせた。止まった先には、大きな門。つられるように青鈍の瞳も同じ方向へ視線を向ける。
「………どうして貴方が待っているんですか」
まわりくどい言い方を好まぬあまり、彼の言葉は直で人の心に忍び込む。それを受け流せず喧嘩腰になる者、逆に冷笑で返す者、或いはそれすら気付かずに愛想笑いを浮かべながら見当違いの答えを弾き出す者。その何れにも属さない反応を返す貴重な存在が、目の前でもう一度微笑った。
目を伏せて小さく溜息をつくと、座っても門が見える場所にぺたりと座り込んでしまう。首を傾げながら、それでもその隣へ歩み寄り同じようにルヴァも草の上に腰を下ろした。手が伸びてきて、膝を抱えようとした腕を取る。引き寄せられるまま手を預け成り行きを見守るルヴァの目の前で、セイランはその手の甲に唇を押し当てた。
「……冷たい」
皮肉のひとつでも言うだろうと想われた唇からは、そんな言葉しか出てこなかった。肩透かしを食らったような、それでも嬉しそうな、複雑な表情でふわりと笑う。
興味なさげに見えて、あれでも結構彼のことが気に入っている、という事実が理由。彼―――――銀色の髪の、ナイフの切っ先のような瞳の彼、を。
「でも、僕は貴方のほうが気になる」
瞳の奥のルヴァの考えに気付いたのか、透明な瞳でルヴァを見る。
「自分のことはそっちのけで、どうしてそんなに他人のことを考えられるんです?」
「さぁ……どうして、でしょうかねぇ」
濁す彼に、思い切り不満気な表情をぶつける。
|