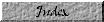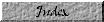|
かたり、と、手を当てられた窓硝子が、小さく音を立てる。触れた指先から伝わる冷気にふるっと肩を震わせ、吐く息が白く色付く様をぼんやりと眺めながら手を引く。
「……雪…」
呟くように落とされた言葉に、部屋の奥、暖炉の傍に置かれたソファが微かに軋む。窓の外へ向けた視線が背後に立つ影を見止め、振り返ろうとする。それを軽く押し留めて細い肩へ大きな手が覆い被さった。
「…珍しいな。聖地で、雪…か」
触れた肩がひやりと冷たいことに気付き、暖めるように包み込んだままゆるりと撫でる。手の感触がくすぐったいのか僅かに肩を竦めて小さく微笑う気配。
「貴方には……似合いませんねぇ」
くすくすと微笑い続ける彼を見下ろしたまま、僅かに眉を潜める。やおら腕を伸ばすと、ぐいっと抱き上げて窓の傍から部屋の奥へと歩き出した。
「何を笑う」
「いえ……なんでも…?」
零れる音は形を潜めたけれど、やはり口の端は微笑っていて。小さくため息をつきながら抱えていた身体をそっとソファへ下ろし、見上げてくる青鈍を見遣り隣へ腰を落ち着ける。
腕を伸ばして肩を抱き、僅かな力で傍へと促す。その微かな力加減に、極自然な仕草で身体を寄せてくる。その動作は思考の外。漸く口元を緩め、紅い髪が微笑に揺れた。
下界では12月と呼ばれる頃。温暖な聖地では珍しく雪が降ったその日、炎の守護聖の私邸を、地の守護聖が訪れていた。
そろそろ夜も更けようという時刻、私室の暖炉脇に据えられたソファに座るふたりの様子は、例えば夢の守護聖等が目撃したなら即刻引き剥がすだろうことが容易に想像できる程に、仲睦まじかった。
紅く揺れる炎の光に照らされた地の守護聖ルヴァの白い頬へ、炎の守護聖オスカーの手が伸びる。柔らかい肌を撫で、そのままするりと輪郭をなぞって頤に掛けられた指が、未だ窓の外を眺めるルヴァの貌を自分の方へ向かせようと動く。微かな抵抗と共に振り向いたその頬に贈られる、柔らかな口付け。微笑みながら小さく首を竦めてみせたルヴァが、彼の貌を僅かに押し戻す。
「……くすぐったいですよ〜」
小さく苦笑を浮かべたまま、オスカーは再度貌を近付け、今度は首筋に貌を埋める。ひくっと肩を震わせたルヴァの白い手が、背後で自分を受け止めている肩口へ思わず伸びていく。いつもならそのまま肌を辿り出すその唇が、ひとつ口付けただけであっさりと離れ、今度は頬が押し当てられた。
頤を引き背後をそっと窺うと、秘色の瞳は先刻ルヴァが立っていた窓の方を見ていて。
「どうか…?」
押さえ気味の声音でルヴァが問う。その首筋に頬を押し当てたままのオスカーは、小さく首を振った。
「いや……なんでもない」
小さく息をつき苦笑すると、同じように青鈍の瞳が窓の外に向けられる。
「…私の育った惑星は……とても乾燥した惑星でしたから。雪は……それだけに、とても興味深いんですよ」
静かなルヴァの声に、ただ、頷きだけが返される。
「貴方の育った惑星も…私の星より幾らか湿潤とはいえ、雪が降るほどの環境にはなかったですよねぇ……?」
「……ああ」
膝の上に置いていた手を持ち上げ、ルヴァは、自分の首筋に貌を埋めたままの彼の頬へその手をそっと添わせた。口元に浮かぶのは、優しげな微笑み。
「私と貴方……両方にとって、更に此処では本当に珍しい…雪、が。なんだか、お祝いしてくれているみたいで……嬉しかっただけ、ですよ?」
何処か拗ねた子供をあやすような仕草で頬を撫で、髪をゆるりと梳く。少し間を置いて、小さく『判ってる』と、オスカーが応えた。それを聞き、またルヴァが小さく微笑う。
|