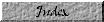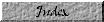|
こつん。
小さくて、小さくて。
あらかじめ鳴ることを知っていなければ聞き逃してしまいそうな程、小さい物音。
字列を追っていた視線が、その物音に呼応したかのように上げられた。テーブルの上の燭台で蝋燭が光を揺らめかせる。その蜜蝋をじっと見つめたまま、表情は先程頁を繰っていた時と全く変わらない。
こつん。
もう一度、今度は先程よりもほんの少し大きい音がした。それでもやはり、聞き耳を立てていないと判らないくらいの、小さい物音に変わりはなく。
無表情だった口元に、ふんわりと笑み。ターバンでテーブルに影を作りながらかたりと立ち上がる仕草は、優雅でいて、何処か急いた印象を与えた。それを見ているのは、ただ、橙の光を燈す、蝋燭だけ。
静かに窓際へ近寄ると同時に、もう一度、こつん、と物音がした。柔らかい微笑を湛えたまま、きぃ、とテラスに続くガラス張りの扉を押し開く。暖かな室内に、冷えた夜気がひっそりと忍び込んだ。
「どうぞ」
穏やかな声が闇に吸い込まれる。程なく、テラスの下で地面を蹴るような音が響き、ぎし、と突然現れた大きな手がテラスの手摺を掴んだかと思うと、舘の主の目の前に、見慣れた巨躯が驚くほど静かに舞い降りた。
「夜分遅く、済みません」
「……いぃえ…御待ちしていましたよ」
青鈍の瞳に、笑みが深まる。
照れたように首を傾げ頭を掻いて、赤銅の髪を揺らす。黄金の双眸が細められ、笑みを返した。半歩寄り添うように近付いて、いつも自分からは部屋に入ろうとしない彼の背に片手を添える。
「冷えたでしょう?……何か暖かいものでも、用意しましょうねぇ」
ガラス張りの扉は、ふたりをその中へと取り込むと、ぱたりと閉じられた。
* * *
大きな重い扉の前で、ひとつ深呼吸。ノックをしようとして、一度手を引っ込めてしまう。息を呑み軽く頷くと、じっと扉を見つめた。
「失礼致します、ルヴァ様」
軽いノックと共に、ともすれば慇懃ととられてしまいそうなほど丁寧な挨拶が響く。重い扉が開かれ、濃い浅葱の髪が深々と沈むのが見えた。ゆっくりと振り返るターバンが軽く傾ぎ、にっこりと微笑う。
「あ〜、これは、珍しいですねぇ、エルンスト。よくいらっしゃいました」
研究院にルヴァが行くことがあっても、やはり彼のほうから執務室へ来ることは少ない。それ故の、一抹の胸騒ぎ。それを打ち消すように、けれどそうと悟られないように、ほんの僅か頭を振り、かたんと椅子から立ち上がる。
人当たりが良い、と評される笑顔を浮かべながら、にこにこと主任研究員を執務室へ招き入れた。御茶でも淹れましょう、と微笑いながらルヴァが椅子を勧めると、お気遣いなさらず、とエルンストはそれを固辞しようとする。頑ななその様子に、ほんの少し困ったような笑みを浮かべて首を傾げた。
「最近、此処に来てくれる皆が皆、御茶も飲まずに帰ってしまうんです。どうせなら、ゆっくりと御茶を飲みながら色々御話ししたいと思いませんか?」
この後、なにか急ぎの用事でも?と問われ、思わず『いいえ』と答えてしまう。嬉しそうににっこり微笑むルヴァの期待を裏切ることは、流石にエルンストにはできなかった。
「……では、少しだけ」
久しぶりの話し相手を得て、もう一度青鈍の瞳が微笑む。聖地に住まう者であれば、その微笑みに勝てる者は居ないだろう。エルンストも御多分に漏れず椅子へと腰を落ち着けざるを得なかった。
地の守護聖と語らう機会などそうそうある筈もない。その機会を得たということは、ひとりの研究員として非常に嬉しいことであり、また恐悦至極とも言えるものだった。……ただ、時としてその頭の回転の速さについていくことができず、ひとり話題に取り残されてしまうような破目に陥ることがあるということと、一旦口を開くと少々話が長い、というような問題はあるのだけれど。
もちろん地の守護聖に御茶を淹れてもらうということなどこれまである筈もなく、エルンストは酷く恐縮しながらカップを手に取った。
「……美味しいです」
ひとくち飲み、無意識に口を突いて出たその言葉に、ルヴァは嬉しそうに微笑った。
|