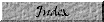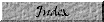|
肘掛のあるゆったりとした椅子に腰を下ろし、膝に置いた本のページをゆっくりと捲る。時には笑みを零し、またある時にはじっと真顔で読み耽る横顔に、何時しか暮れかけた日の光が降りかかる。翳り始めた手許に気付いて顔を上げ、オレンジ色に染まり始めた戸外の風景に暫し見入った。
「―――――もう、日が暮れますねぇ」
首を傾げる風な仕草に、ターバンの結び目から伸びる布がゆらりと揺れた。本を傍らのテーブルへ預けて立ち上がり、侍従を呼ぶ。以前自分で部屋の明かりを点けようとしたときに踏み台から落ち足を挫いてしまったため、自ら明かりを点けることを止められている。『次はちゃんと点けられると思うのですけれどねぇ』と思っているのは本人だけだった。
ややしてやってきた侍従が火を点すと、暗くなり始めていた部屋にオレンジ色の光が広がる。仄かな、そして暖かな光に眼を細める主へと深々と頭を下げた侍従は、静かに部屋を退出していった。
カーテンを半分ほど引き、テーブルへと向かう。夜に本を読むときいつも使っているランプを手に取り、オイルの残りを確かめてからシェードを外した。長年使っているランプだけに手馴れた様子で火を入れていく。
シェードを被せたところで、ふと何かに気を取られたかの様に動きが止まり、ランプへと注がれていた視線がゆるりと空を流れていく。
「そう…下では……一年が終わる日、なんですね」
仄明るい光に照らされた姿が、机の隅に置かれた小さな暦を見下ろす。果てしなく緩やかに流れる聖地の時間と、かつては己も身を置いていた下界の時間、双方を一目で追える様に作られた暦の、最後の一日へと指を伸ばす。
愛しい何かを確かめる様に小さな欄をなぞり、青鈍が僅かに緩んだ。
『本当にいいのね』
酷く心配そうな声で問いかける母親の声が甦る。
『必要としてくれる人が居るから、…大丈夫です』
自分以外に替わることが出来る者が居ないのなら、行くしかない。それならせめて、もう二度と会えないだろう母を少しでも安心させてやれるよう、笑顔で。
『そう……、精一杯、頑張りなさい』
はい、と頷き、最後の抱擁にしっかりと腕を伸ばして、母の身体を抱きしめた。
課せられた役目のために今迄居た時間の流れから外れ、永遠と見紛う程緩やかに流れる日々へと身を置かねばならぬ現実。己が足で実際に地を踏みしめ歩いていた時代と、現在の自分の間に横たわる、気が遠くなる程に広い広い隔たり。その全てに眼を瞑り、聖地に流れる時間だけを追うことも出来る。けれど、下界の歴史と聖地の歴史を等しく認識した上で全てを見渡さねば全う出来ない本分故に、気が遠くなる程の隔たりから眼を逸らせない。
もう一度暦を撫でてからランプへと手を伸ばし、軽く掲げながら先刻本を読んでいた椅子へと戻る。傍らの机にランプをそっと下ろしてから椅子へ腰掛けた。背凭れに身体を預け、そっと眼を閉じる。瞼の裏に柔らかな光を感じながら、身体から力を抜いた。
聖地へ来たばかりの頃を思い返せば、最初は慣れぬ環境と見知らぬ人々の間に突然放り込まれ右往左往していた自分が脳裏に浮かんでくる。呼び止められる度に何か叱責を受けるのではないかと必要以上に萎縮していた時期もあった、と苦笑が零れる。
|